【前回のおさらい】織田信長の天下統一事業
前回は織田信長の天下統一事業を解説していきました。あと一歩というところで,家臣の明智光秀に裏切られ,本能寺の変でその生涯を終えましたね。
今回は安土桃山時代のうち,豊臣秀吉が行ったことを解説していきます。
中学校で習う内容に絞って,簡潔に流れをまとめています。ここで学んだ基礎知識をもとに,より興味が湧いた!もっと詳しく知りたい!という方は色々調べてみてください!
織田信長の天下統一事業はこちらから!
では百姓から天下を統一した,日本史上最高の出世を果たした秀吉の歴史を見ていきましょう!
日本史をまとめるにあたって,参考にした資料は以下の2冊です。
豊臣秀吉 個人史
1582年,明智光秀の裏切りを知った秀吉は,山崎の戦いで明智光秀を倒す
⇓
信長の後継者争いにも勝利し,本拠地として大阪城を築く
⇓
1585年,朝廷から関白に任命され,豊臣の姓をもらう
⇓
1590年,様々な地域の大名を降伏させ,全国統一
⇓
秀吉は日本だけでなく全アジアを支配しようと考え,まず明を攻めるため朝鮮に出兵する(朝鮮出兵)
1592年に1度目の出兵(文禄の役),1597年に2度目の出兵(慶長の役)を行うがどちらも失敗
さらに1598年には秀吉も病死したため中止
秀吉の政策
・バテレン追放令…初めはキリスト教を容認していたが,長崎でキリスト教勢力が拡大していることから,1587年に宣教師の国外追放を命じた
・太閤検地…地域によって異なっていたものさしやますを統一し,全国の田畑の面積や
土地の良し悪しを調べ,予想される収穫量を石高で示した
・刀狩…農民や寺社から武器を取り上げ,一揆を防いだ
⇒武士と農民の区別が明確になる(兵農分離)
豊臣秀吉 個人史 解説
山崎の合戦
明智光秀が裏切る本能寺の変が起きたとき,秀吉は中国地方にいて,毛利氏と戦っていました。
しかし信長の死の知らせを聞くと,毛利氏との戦いをやめて和睦を結び,すぐに京都まで向かいました。
これがあまりの速さだったため「中国大返し」と呼ばれています。そして明智光秀を倒すことに成功します。
明智光秀は当時最も権力を握っていた織田信長を倒すことに成功しましたが,わずか13日で豊臣秀吉に敗れてしまいました。
この出来事から,「権力を握っている期間がきわめて短いこと」を「三日天下」と言います。
「三日」とは,3日間のことではなく,ごく短い期間のことを指します。
ちなみに明智光秀といえば『麒麟がくる』ですが,『麒麟がくる』をはじめとする大河ドラマは,U-NEXT内にある「NHKオンデマンド見放題パック」を利用することで好きなだけ見ることができます!今放送中の『どうする家康』もなんと見放題です!
「NHKオンデマンド見放題パック」は月額990円(税込)ですが、U-NEXTは登録後31日間は無料となります。
さらにU-NEXTの初回登録時に1,000円分のポイントが付与されちゃいます!
2か月目以降も毎月1,200円分のポイントが付与されるので,つまりその後もU-NEXTの月額料金のみで大河ドラマも見放題ということです。
清洲(清須)会議
織田信長の死を受けて,次に大きな問題となったのが織田家の後継ぎを誰にするかという点です。
後継ぎについて話し合うために,尾張の清州城に主要人物たちが集まります。これが清洲会議です。
この後継者争いに秀吉は勝利し,1583年には大阪城も建てて天下統一に動き出します。

清州会議の詳細はかなり長くなってしまうため割愛しました。書籍や映画にもなっているので,興味がある方はぜひ見てみてください!
関白となり豊臣の姓をもらう
天下統一に向けて動きを強めた秀吉ですが,困ったことが1つありました。
それは,天下をとるためにはそれ相応の身分が必要だけど,秀吉は元々百姓の出身であるということです。
1番上に立つ人間がただの百姓というのは,いくら強くても威厳がないですよね。当時は家柄がとても大切な時代です。命令に従わない者が出てくる可能性もあります。
そのため秀吉は武士の最高位の役職である「征夷大将軍」に就きたかったのですが,信長に追放された室町幕府15代将軍の義昭がその職を手放しませんでした。
そこで秀吉は,元関白だった近衛前久の養子となることで,1585年に「関白」という地位を手に入れました。
関白とは,天皇が成人後も政治の補佐をする,天皇に次ぐ最高位の役職です。
これによって天下統一のために必要だった地位も手に入れ,翌年に朝廷から「豊臣」の姓をもらいました。(これ以前は「羽柴秀吉」という名でした)
全国統一
課題だった地位も手にした秀吉は,九州・四国・東北の諸大名を次々と従え,1590年に小田原(神奈川)の北条氏を滅ぼして全国統一を成し遂げます。
朝鮮出兵
全国統一を果たした秀吉は,次はアジアを支配しようと海外に目を向けます。最初のターゲットは明(中国)で,明を攻めるためにその手前の朝鮮から攻撃しました。
これが1592年の文禄の役で,最初は勢いが強く漢城(今のソウル)まで占領しました。
しかし朝鮮の将軍・李舜臣が亀甲船を駆使して日本軍を返り討ちにしました。さらに明からの援軍もあったため,一度日本は攻めるのを諦めます。

1597年に二度目の攻撃を仕掛けますが(慶長の役),翌年に秀吉が病死してしまったため,戦いも中止となります。
この戦いは多大な被害を生んだため,豊臣氏に対する不満が一気に高まりました。ここから豊臣氏は没落していくことになります。
また,朝鮮出兵によって朝鮮から日本に優れた陶工が連れ帰られました。この人々は陶磁器の製法を伝え,有田焼(佐賀)などが生まれました。
秀吉の政策 解説
バテレン追放令
フランシスコ・ザビエルが来日してから,キリスト教信者が急激に増えました。そのため秀吉はキリスト教宣教師の国外追放を命じます。
この理由については諸説あります。キリスト教徒が反乱を起こすのを恐れたためや,キリスト教徒が仏教徒などを迫害したため,とも言われています。
しかし秀吉は南蛮貿易はある程度推奨していたので,徹底したキリスト教の禁止とはなっていません。
太閤検地と刀狩
太閤検地の内容は,「秀吉の政策」で書いた通りとなります。「太閤」とは,関白を辞めた人の称号です。
刀狩も先ほど説明した通りで,これによって「身分の低いものが高いものを実力で倒す」という下剋上の世は終わりを告げました。
豊臣秀吉 まとめ
以上が秀吉が行ったこととなります。
最初の年表は中学校でほぼ確実に習う内容です。解説は中学校では扱わないような,ちょっとプラスアルファの内容も入っています。
何を学ぶにしても,まずは基本をしっかり理解して土台を作ってあげることです!この記事を土台にして,そこから自分で調べてさらに積み上げていってください。また,そこで知った知識を私にも共有してもらえると大変うれしいです!
知識はアウトプットすることで初めて定着します。アウトプット相手にも,ぜひこのブログを活用してください!





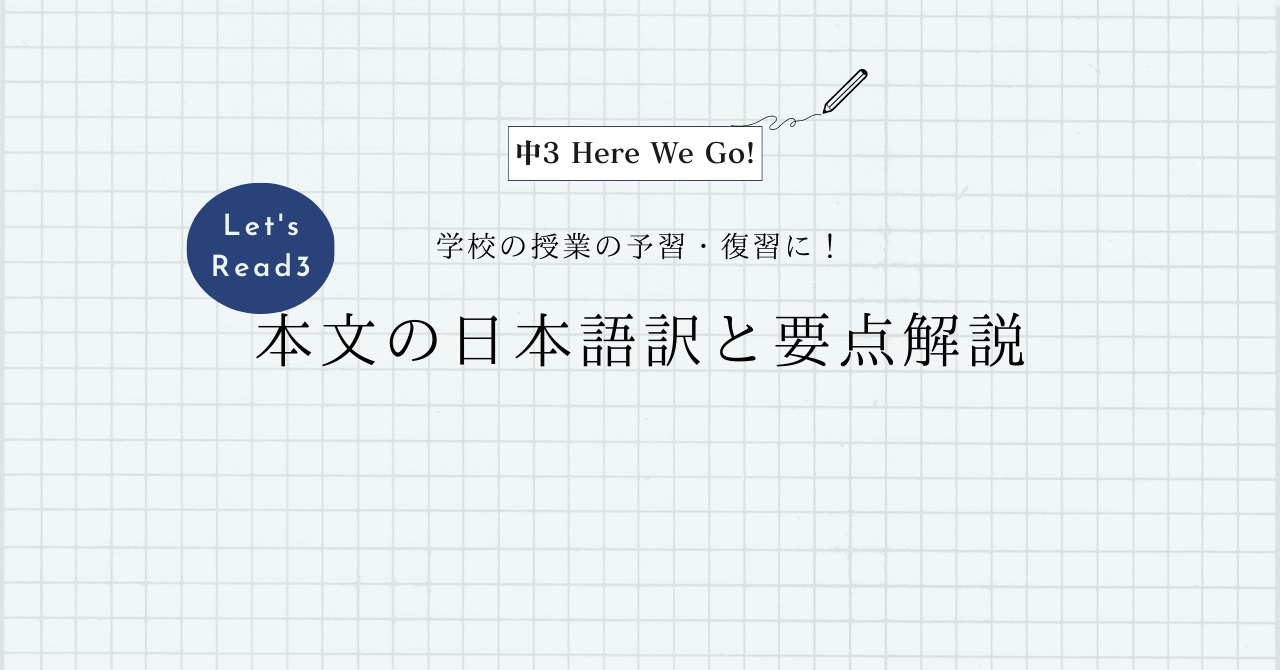
コメント